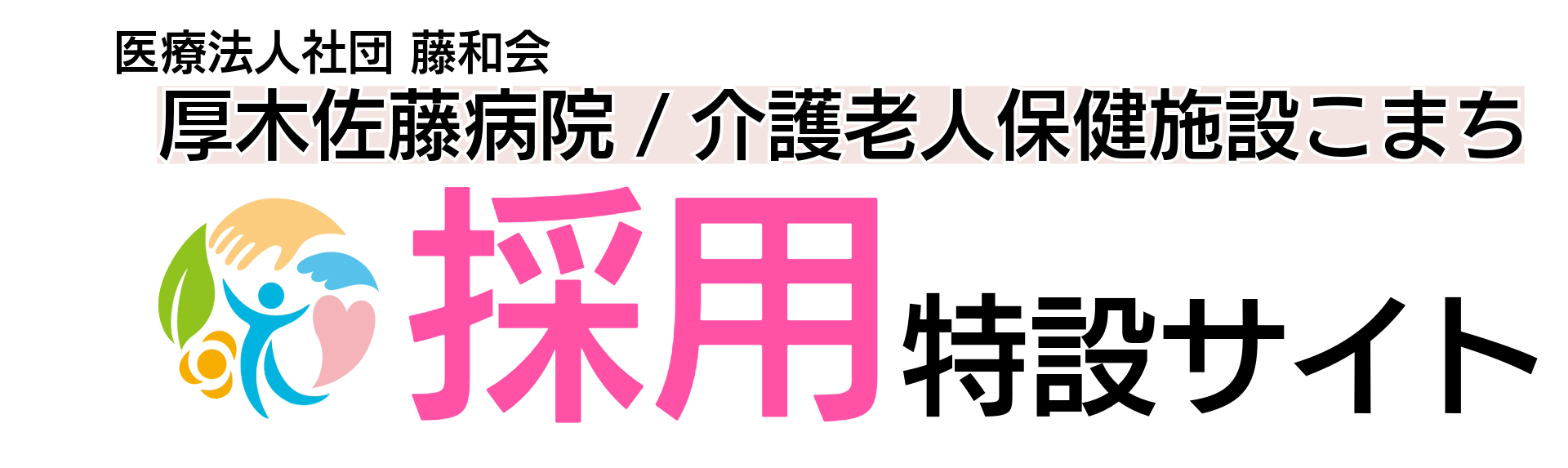厚木佐藤病院のリハビリテーション課は、患者様の「自分らしい生活」を支えるため、日々奮闘しています。今回は、勤続20年以上のベテラン、リハビリテーション課の課長に、当院リハビリテーション課の魅力と今後の展望についてお話を伺いました。
Q. 厚木佐藤病院のリハビリテーション課は、どのようなチームですか?
課長:当院のリハビリテーション課は、私が勤務し始めた当初の20年以上前のPT5名から、現在PT8名(育休除く)、OTは2~3名から11~12名(育休除く)、STも0名から3名(育休含む)と、この20年間で大きく成長を遂げてきました。特にOTは大幅に増員していますね。
スタッフの平均年齢は比較的低く、若手が多いこともあり活気があります。しかし、ただ人数が多いだけでなく、患者さん一人ひとりに深く関われるのが当課の大きな特徴です。例えば、医師とはカンファレンスや電子カルテ内のメール機能で指示のやり取りをする一方、病棟スタッフとは患者さんの状態を密に連携し、リハビリスタッフが患者さんと一番話す機会が多いからこそ、信頼関係を築き、患者さんの代弁者として病棟スタッフとの「つなぎ役」も担っています。
Q. どのような患者さんが多く、どのようなリハビリテーションを提供していますか?
課長:当院の患者層は、高齢者、特に認知症を伴う方や重症度の高い方がメインです。肺炎や脱水などで入院される方も多く、当院は「認知症を見る病院」という病院イメージもあるようです。
リハビリテーションにおいては、「早期介入・早期離床」を重視し、患者さんのADL(日常生活動作)向上と、患者さんやご家族が希望される場所への退院を目標に掲げています。環境に合わせたリハビリを考え、必要であればご家族にもリハビリを見学してもらい、退院先での生活をイメージできるよう支援しています。
PTは歩行など基本動作、OTはADL全般を、STは特に嚥下(えんげ)機能の改善に力を入れています。高齢者の嚥下障害は非常に多く、食事を通して患者さんの生活の質とモチベーション向上に貢献できる、やりがいのある分野です。
また、当院は「身体抑制をしない」ことを掲げており、転倒予防にも力を入れています。入院初期の転倒を減らすため、行動要因へのアプローチを強化し、患者さんへの説明や環境整備、病棟との連携を徹底するなど、継続的に取り組んでいます。
Q. リハビリテーション課で働く「やりがい」や「成長の機会」について教えてください。
課長:やはり一番のやりがいは、患者さんが回復し、ご自宅など希望される場所へ退院できた時、そして「ありがとう」と感謝された時です。最近も、入院時は怒ってばかりでADLも介助量が多かった患者さんが、関わりを通して笑顔を取り戻し、退院後も定期的に絵はがきを送ってくれたエピソードは、私たちにとって大きな喜びです。
若手スタッフの成長をサポートするため、今年度は課内でグループに分かれて、文献抄読や実技を共有する勉強会を定期的に開催しています。また、3年目までの若手には地区のリハビリ連絡会での発表を推奨しており、PT協会が始めた「登録理学療法士・作業療法士」のような基礎研修の受講も推奨し、協会主催の研修費用は年度に1回支給される制度もあります。
新しいことに挑戦したいという意欲的な方には、「もうどうぞどうぞ、バックアップします」というスタンスです。院長も新しい取り組みには理解があり、良い提案であれば「いいんじゃない?」とGOサインを出してくれる環境です。当院は、大きな病院では難しい、「自分で考え、色々なことを試せる」自由な風土が特徴であると思います。
Q. 今後、どのような人材を求めていますか?
課長:私たちは、「自主的に考え、行動できる人材」を求めています。現在の若手には、基本的なリハビリプログラムの質向上や、自分から積極的に勉強する姿勢が課題だと感じていますが、これは裏を返せば、新しいスタッフが自身のアイデアや知識を活かし、リハビリテーション課全体の質を高めていく大きなチャンスがあるということです。
患者さんの状態が多様化し、認知症や重症度の高い方が増える中で、マニュアル通りではなく、目の前の患者さんのために何ができるかを考え、創意工夫できる方を歓迎します。当院リハビリテーション課の「笑顔の輪」という理念のように、患者さんの笑顔を引き出すために、一緒に挑戦していきましょう。